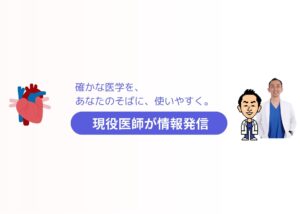はじめに
人生の3分の1は睡眠に費やされています。
睡眠不足は日中の眠気や意欲の低下、疲労感を感じるなど精神・身体面への影響だけでなく、高血圧や糖尿病などの生活習慣病や心臓疾患にとって悪影響を及ぼします。
しかし、病院で勤務していると、患者さんから「よく眠れていない」、と言われることが非常に多いです。
入院患者さんでは、体調の問題(息苦しさ、術後の傷の痛み、安静に伴う腰痛など)や環境の変化(マットレスや枕が合わない、大部屋での物音など)が原因としては多いように感じます。また、退院後の方であっても、体調への不安や利尿剤の影響で夜間に何度もトイレに行く、など様々な理由が挙げられます。
そこで今回は、睡眠と心臓病の関係についてと、睡眠不足への対策法について解説します。
日本人の睡眠時間について
NHK放送文化研究所が5年ごとに行なっている国民生活時間調査の結果によると、2020年の日本人の睡眠時間は平均で7時間12分(男性:7時間20分、女性:7時間6分)となっており、ここ10年は横ばいで経過しています。
しかし、60歳以上となると、ここ5年で男女ともに睡眠時間が短縮しています。
また、世界と比較すると、日本は睡眠時間が世界で最も短い国であることが知られています。経済協力開発機構(OECD)の「Gender date portal 2019」によると、日本人の平均睡眠時間は7時間22分で、イギリスの8時間28分、アメリカの8時間47分などと比較して1時間以上も短いのです。
睡眠の問題は、特に日本で大きな問題ですし、その中でも60歳以上では深刻化しているのかもしれません。
睡眠障害とは
ひと口に睡眠障害と言っても、様々な種類があります。睡眠障害国際分類(ICSD-3:International Classification of Sleep Disorders,Third Edition)では、以下の7種類に分類されています。
- 不眠症
- 睡眠関連呼吸障害群
- 中枢性過眠症群
- 概日リズム睡眠・覚醒障害群
- 睡眠時随伴症群
- 睡眠関連運動障害群
- その他の睡眠障害
詳細な説明は省略させていただきますが、この中でイメージしやすいのは①不眠症と、②睡眠関連呼吸障害群だと思います。
①不眠症:なかなか寝付けない(入眠困難)、夜中に何度も目を覚ます(中途覚醒)、もしくは朝早くに目が覚め(早朝覚醒)、再び眠りに戻ることが難しいことが特徴です。
②睡眠関連呼吸障害群:睡眠時無呼吸、と説明するとイメージしやすいでしょうか。睡眠中に頻回に呼吸が停止したり、呼吸が浅くなる状態を言います。肥満の方がよく発症しているように思うかもしれませんが、心不全が重症化してしまうと肥満でない方も発症してしまう可能性があります。
心臓病の方の睡眠障害(睡眠時無呼吸)の有病率
睡眠障害の検査では、睡眠中にどれくらい呼吸が停止したり、呼吸が浅くなったかを測定し、睡眠障害の重症度を判定しています。
以下は、軽症(1時間あたりの呼吸に5~15回異常がある場合)の睡眠障害を保有している割合です。
- 急性冠症候群(狭心症、心筋梗塞)患者・・69%
- 心不全・・69.3〜76%
- 心房細動・・81.4%
- 高血圧・・59%
- 糖尿病・・86%
(日本循環器学会.循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン 2023年改訂版)
睡眠障害の心臓病への悪影響
では、睡眠障害があると心臓病にどのような影響があるのでしょうか。
Huangらは、睡眠の質と心臓病の発症との関係について研究しています。この報告はイギリスのデータベースに登録されている30万人以上の心臓病を有していない人のデータを解析したものになります。
睡眠の質が悪いと、解析の結果、心臓病の発症のリスクが男性で1.13倍に、女性で1.17倍になるとされています。睡眠の質が悪いと平均して男性では2.31年、女性では1.80年心臓病を早く発症すると推定されています。
特に睡眠関連呼吸障害(睡眠時無呼吸)があると、臓病の発症のリスクが男性で1.83倍になり、女性で2.09倍になるとされています。睡眠関連呼吸障害がある集団では平均して男性では6.73年、女性では7.32年心臓病を早く発症すると推定されています。 (BMC Medicine:2023;21:75)
Kwokらは過去の複数の研究結果をまとめたものを報告しています。これは全米睡眠財団(The National Sleep Foundation)が推奨している睡眠時間(26-64歳:7〜9時間、65歳以上:7〜8時間)と比べ、長いもしくは短い睡眠時間が心臓病(ここでは心筋梗塞や狭心症)にどれくらい影響を与えるかを報告しています。
その結果、睡眠時間が6時間になると1.08倍、5時間になると1.49倍心臓病になる確率が上がるとされています。また、睡眠の質も重要で、睡眠の質が悪いと感じた人は1.44倍心臓病になるとされています。(J Am Heart Assoc. 2018.7;7(15):e008552)
適切な睡眠をとるために
厚生労働省の研究版によって、睡眠障害を事前に防ぐための方法をまとめた「睡眠障害対処 12の指針」というものがまとめられています。
①睡眠時間は人それぞれ、日中の眠気で困らなければ十分
・睡眠の長い人、短い人、季節でも変化、8時間にこだわらない
・歳をとると必要な睡眠時間は短くなる
②刺激物を避け、寝る前位には自分なりのリラックス法
・就床4時間前のカフェイン摂取、就床前1時間の喫煙は避ける
・軽い読書、音楽、ぬるめの入浴、香り、筋弛緩トレーニング
③眠たくなってから床に就く、就床時刻にこだわりすぎない
・眠ろうとする意気込みが頭をさえさせ寝つきを悪くする
④同じ時刻に毎日起床
・早寝早起きでなく、早起きが早寝に通じる
・日曜に遅くまで床で過ごすと、月曜の朝がつらくなる
⑤光の利用で良い睡眠
・目が覚めたら日光を取り入れ、体内時計をスイッチオン
・夜は明るすぎない証明を
⑥規則正しい3度の食事、規則的な運動習慣
・朝食は心と体の目覚めに重要、夜食はごく軽く
・運動習慣は熟睡を促進
⑦昼寝をするなら、15時前の20〜30分
・長い昼寝はかえってぼんやりのもと
・夕方以降の昼寝は夜の睡眠に悪影響
⑧眠りが浅い時は、むしろ積極的に遅寝・早起きに
・寝床で長く過ごしすぎると熟睡感が減る
⑨睡眠中の激しいイビキ・呼吸停止や足のぴくつき・むずむず感は要注意
・背景に睡眠の病気、専門治療が必要
⑩十分眠っても日中の眠気が強い時は専門医に
・長時間眠っても日中の眠気で仕事・学業に支障がある場合は専門医に相談
・車の運転に注意
⑪睡眠薬代わりの寝酒は不眠のもと
・寝酒は、深い睡眠を減らし、夜中に目覚める原因となる
⑫睡眠薬は医師の指示で正しく使えば安全
・一定時刻に服用し就床
・アルコールとの併用をしない
また、日本循環器学会のガイドラインでは、有酸素運動と筋力トレーニングを実施することで睡眠障害が改善したという報告を受けて、運動を実施することを強く推奨しています。
適切な運動強度で、定期的な運動を実施すること、つまり心臓リハビリーテーションで行う事を習慣づけることで、睡眠の質を改善することにも繋がるのです!
まとめ
- よい睡眠を確保する事は睡眠時間が短い日本で暮らす私たちの大きな課題です。
- 特に心臓病を患う人は睡眠障害に悩まされることが多いです。
- 十分時間のよい睡眠をとる事は、生活習慣病や心臓病の悪化を防ぐために重要です。
- 適度な運動、食事の時間や睡眠前のアルコール摂取を控える、寝室の環境の調整などにより睡眠を改善させましょう。
- 心臓リハビリテーションという治療もありますし、心臓病の方はいろいろなサービスを利用して適度な運動を取り入れてください。