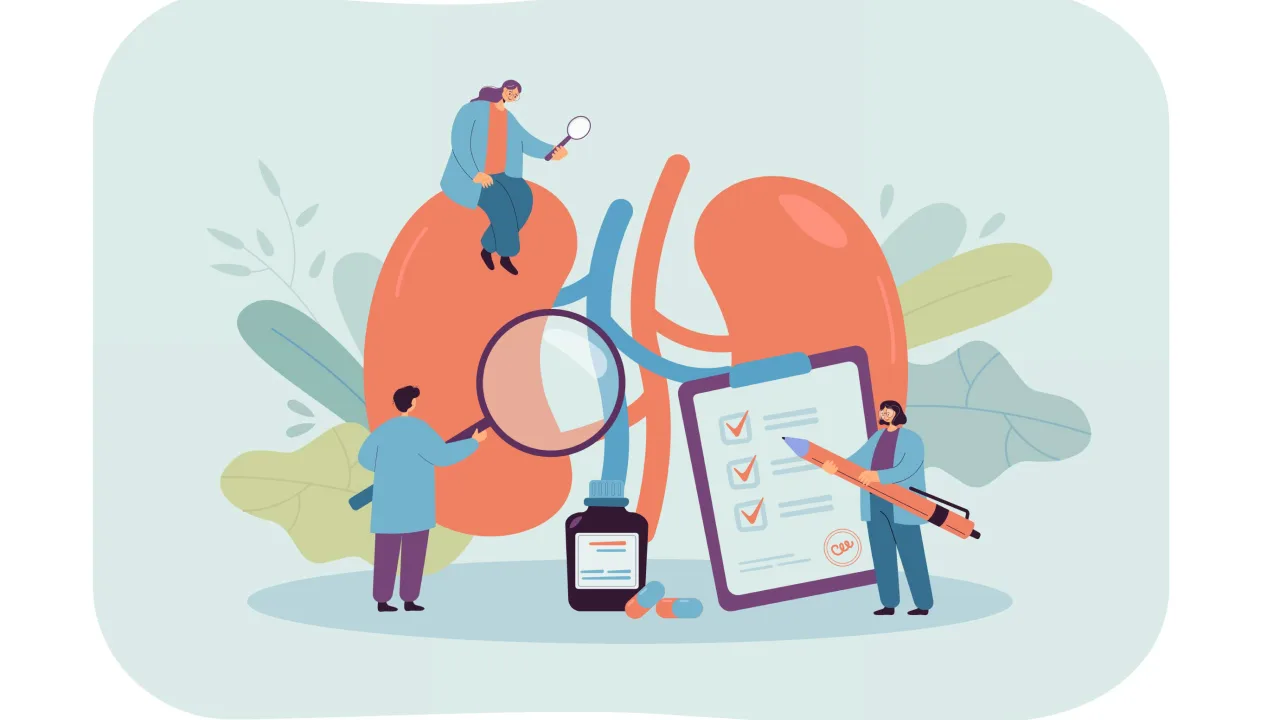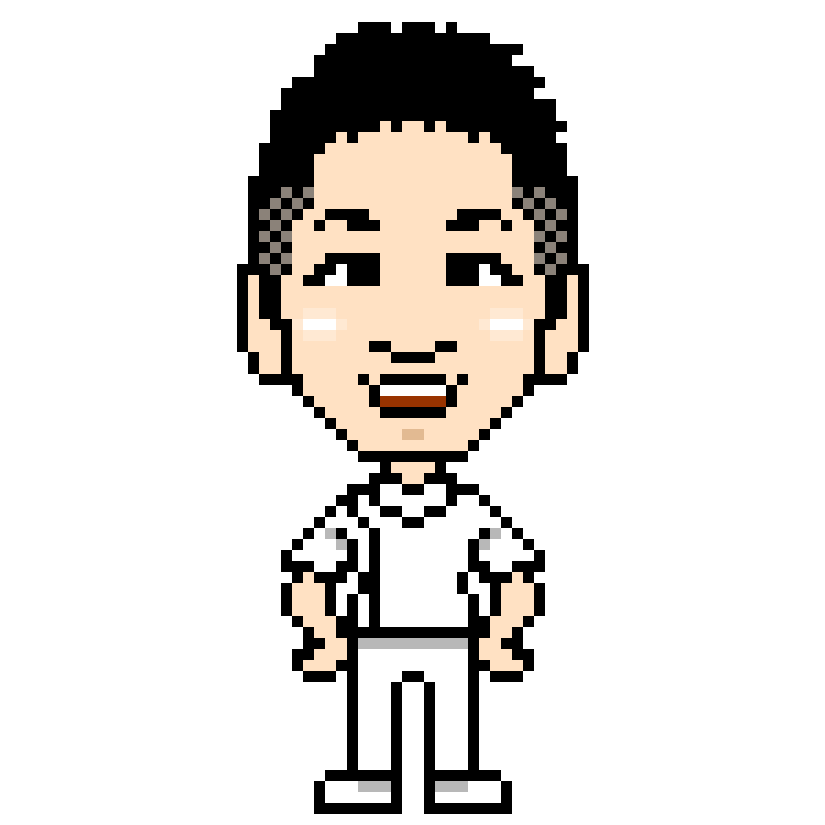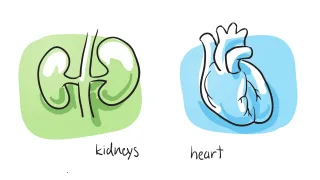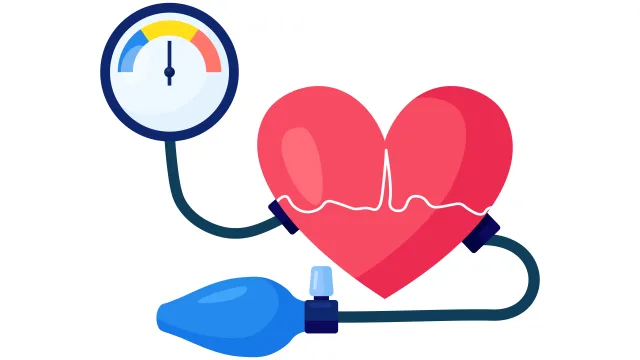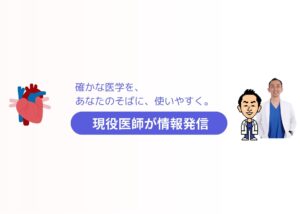先生から、あなたは心臓だけでなく腎臓の機能も低下しています、と言われたけど、何も症状がないんです。腎臓が悪いとどんな影響があるの?
腎臓と心臓は密接な関係にあります。腎臓の機能を維持することは、ご自身の心臓を守るためにも重要なのです。
今回は腎臓の役割についてまとめます。
「若いうちから、腎臓検診」と、島耕作が出演しているテレビCMを目にした方もいるのではないでしょうか。日本腎臓財団が慢性腎臓病予防のための事業として作成したものです。今、日本人の成人の8人に1人が腎臓の機能が低下した状態であると推定されています。腎臓の機能が少し低下しているくらいでは何も症状はありません。しかし、腎臓病は心臓病と密接な関係性にあり、腎臓の機能が悪くならないように早くから対策を取る必要があります。
本記事の内容のダイジェストを1分間の動画でまとめています。
腎臓の働きについて
腎臓は腰のあたりにある、そら豆のような形をした、握り拳くらいの大きさの臓器です。
役割は主に3つあります。
- 尿を作る:体の中の老廃物を尿として排泄します。この時、必要なものは再度体の中に吸収します。
- 体のバランスを調整する:体の中の水分量、ナトリウムやカリウムなどの量を調整しています。
- ホルモンを作る:腎臓では赤血球を作るホルモン、血圧を調整するホルモン、骨を丈夫にするために必要なホルモンを作っています。
腎臓はフィルターのような構造をしています。そのフィルターに血液が流れ、老廃物や余計な水分が濾過され、尿として排泄されます。その尿の元になるもの(原尿)は、なんと1日あたり約150Lも作られています。しかし、そのうちの約99%は体に必要なものも含まれているので、必要な分は再び吸収されています。
腎臓の機能が低下すると、体の水分バランスが崩れむくみが出たり、本来は出るはずのないタンパク質が尿の中に漏れ出してしまいます。ただし、これも初期段階ではほとんど症状が出ません。重症になってからではもう手遅れになってしまうので、普段の検査結果でも少し気にしてみてください。
腎臓の検査
普段の血液検査の結果の中に、腎臓の機能に関係している項目があります。
①クレアチニン(Cre)
クレアチニンは筋肉の中にあるクレアチンという物質から作られる物質です。クレアチニンは毎日同じ量が作られ、全て尿の中に排泄されます。つまり、腎臓の機能が正常であれば、血液の中には少ししか残らないため、血液検査でのクレアチニンの数値は小さくなるのです。反対に、腎臓の機能が低下していると、クレアチニンの数値は大きくなります。
クレアチニンの正常値は、以下のようになっています。
男性:0.61~1.04mg/dL
女性:0.47~0.79mg/dL
クレアチニンは腎臓の機能を表す有用な指標なのですが、一つ弱点があります。それは筋肉の量に強い影響を受ける、という点です。男性と女性で正常値が異なるのもこういった理由からです。痩せている人や運動不足で筋肉量が少ない人では、腎臓の機能が低下していても、採血の結果上はクレアチニンの値は小さくなってしまうので、注意が必要です。
②尿素窒素(BUN)
尿素窒素は血液の中にある尿素の量を表す指標です。尿素はタンパク質から作られる物質です。尿素もクレアチニンと同じように腎臓で一度全て濾過され、大部分が尿として排泄されます(一部は体内に再び吸収されます)。つまり、腎臓の機能が低下すると、尿素窒素の数値も高くなります。
尿素窒素の正常値は、8.0~20.0mg/dLです。
尿素窒素も様々な影響を受けるため、結果の解釈には注意が必要です。1つ目は食事による影響です。尿素はタンパク質から作られる物質なので、タンパク質を多く摂取すると尿素が多く作られるので、血液の中の尿素の量が増えてしまいます。2つ目は、消化管出血による影響です。食道や胃から出血していると、その血液が吸収され、肝臓で最終的に尿素に変えられ血液の中をめぐります。3つ目は脱水の影響です。脱水状態になると、一度腎臓で濾過された尿素が再び体内に吸収される量が増えるため、血液の中の尿素の量が増えます。
このように尿素窒素は様々な影響を受けるため、単独で腎臓の機能を反映するわけではなく、クレアチニンやその他の指標と合わせて解釈されることが多いです。
③糸球体濾過量(しきゅうたいろかりょう:GFR)
糸球体濾過量は腎臓がどれだけの血液を濾過しているか、を表している数値になります。単位はml /minで、1分間でどれだけの血液を濾過することができるのかを表します。ただし、糸球体濾過量を正確に検査するには、24時間の間に出る尿を全て溜めて検査する必要があり、非常に手間がかかります。
そこで、普段の採血では先ほど説明したクレアチニンと、年齢、性別から計算した推定の値が記載されていることが多いです。あくまで推定の値のため、小文字の‘e’ (推定を意味するestimated) がついたeGFRとして表示されています。これも男性と女性で計算式が少し異なっています。一般的にeGFRが60より小さいと、腎臓の機能が低下している、と判断されます。
ここまで3つの指標を説明しましたが、他にも様々な指標が腎臓の機能を表すことがわかっています。ただし、ここに挙げたもの以外は普段の採血ではあまり行われることがないので、詳しい説明は省略させていただきます。
腎臓の機能が低下した状態=’腎不全’とは
腎不全とはその名の通り、腎臓の機能が低下した状態を表します。心臓の機能が低下した状態を‘心不全’と呼ぶのと同じです。腎臓の機能は一度低下すると、元に戻ることはありません。最近は運動によって腎臓の機能が良くなるという報告がありますが、劇的に良くなることはありません。腎臓の機能が低下すると、腎臓の重要な役割であるフィルターの役割を果たす構造(糸球体:しきゅうたい)が、どんどん壊れていってしまうからです。そら豆のようにつるんとしていた腎臓は、干しそら豆のように、小さくなり固くごつごつした形になります。
そのため、腎臓の機能が低下している方には、これ以上腎臓に負担をかけないように食事制限を行ったり、血圧をコントロールしたりする必要があります。つまり、現状維持が基本的な考え方です。
腎臓の機能が長期間にわたって低下した状態を「慢性腎不全」と言います。英語ではCKD:chronic kidney diseaseと表記され、以下の基準のいずれか、または両方が3ヶ月以上続いている状態と定義されています。
- 腎障害:たんぱく尿(微量アルブミン尿を含む)などの尿以上、画像所見や血液検査、病理初見で腎障害が明らかである状態
- 腎機能の低下:血清クレアチニン値を元に推算した糸球体濾過量(eGFR)が60ml /分/1.73㎡未満の状態
腎不全の状態はeGFRの数値によって重症度が区別されています。
| GFR区分(ml/分/1.73㎡) | G1 | 正常または高値 | 90以上 |
| G2 | 正常または軽度低下 | 60~89 | |
| G3a | 軽度~中等度低下 | 45~59 | |
| G3b | 中等度~高度低下 | 30~44 | |
| G4 | 高度低下 | 15~29 | |
| G5 | 末期腎不全 | 15未満 |
eGFRの数値が15よりも小さくなると末期腎不全と判断され、透析の導入が検討されます。腎臓の機能を悪化させる要因は、糖尿病や高血圧、肥満といった生活習慣病が主です。これは心臓病も同じですよね。普段の生活習慣を変えることで、心臓だけでなく腎臓の機能も守ることができます。
腎不全の症状
腎臓の機能が低下した「腎不全」となると、本来、体にとっては不要な老廃物が体にどんどん溜まっていきます。しかし、腎臓の機能が少し低下しただけでは症状はほとんどありません。むしろ腎臓の機能が低下してなんらかの症状が出ている場合は、腎不全がかなり進行した状態であると言えます。
なんらかの症状が出た状態を「尿毒症」と言います。この状態になると透析を考慮しなければいけないくらいの状態です。尿毒症になると、以下の症状が特に多く発生します。
- 消化器症状:食欲の低下、嘔気・嘔吐など
- 中枢神経症状:倦怠感、集中力低下、うつ状態など
また、体の中の余計な水分も排泄されなくなるので、体の中に水分が溜まってしまい、心臓への負担が増加することにもつながります。
まとめ
- 腎臓は体の中の老廃物を出すフィルターの役割をしています。
- 血液検査の項目にある、eGFRという項目が腎臓の機能を表しています。
- 腎臓の機能が低下した状態を腎不全といいます。
- 腎不全になってもほとんど症状はありません。
心臓病と腎臓病は密接な関係にあります。次は、腎臓病と心臓病の関係について勉強しましょう↓