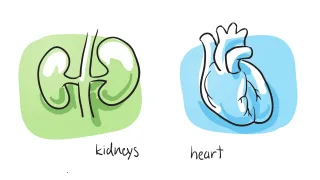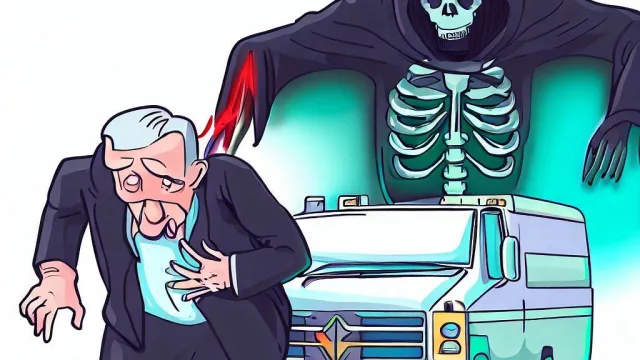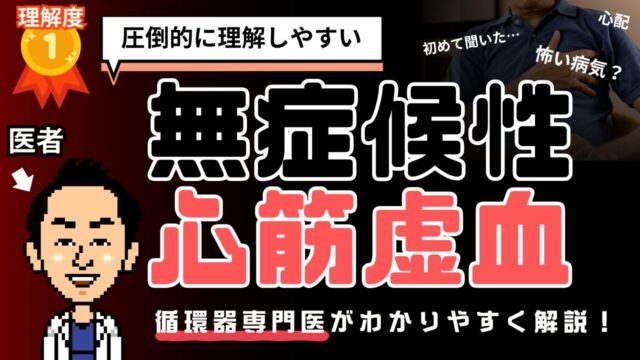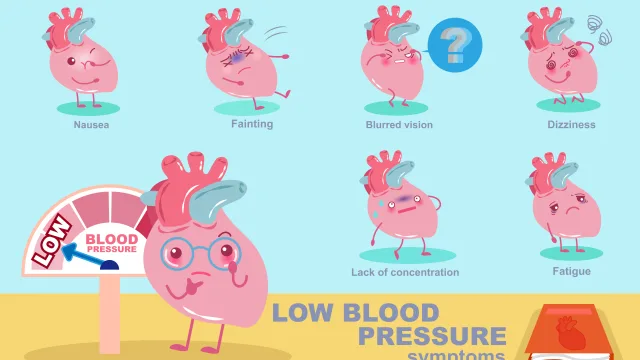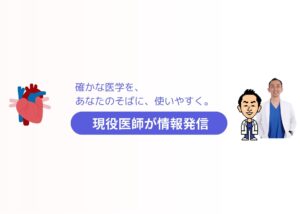糖尿病は心筋梗塞や脳卒中の原因となる生活習慣病の一つです。2019年の「国民健康・栄養調査」では成人に占める「糖尿病が強く疑われる者」の割合は男性19.7%、女性10.8%という結果でした。年齢別にみると65〜74歳では22.6%、75歳以上では21.5%と、年齢が高くなるにつれて糖尿病を合併している人が増えているのです。
糖尿病はなり始めの頃は症状がありませんが、進行すると命に関わる病気です。今回は糖尿病の基本的な知識や対策についてまとめました。
本記事は理学療法士が確かな医学知識を基に執筆し医師が監修しました。ご自身が糖尿病と言われたり、身の回りの方が糖尿病と言われて、情報収集している方にはぜひ最初に読んで頂きたい内容になっています。
糖尿病とは
糖尿病は「インスリンの作用が十分でないためブドウ糖が有効に使われずに血糖値が普段より高くなっている状態」、と定義されています。
ご飯やパン、麺類といった炭水化物は、消化されると最終的にブドウ糖となり、血液の中に入ります。そして血液の中にブドウ糖が多くなる(=血糖値が上がる)と、膵臓が感知してインスリンを血液の中に出します。インスリンは、ブドウ糖を筋肉や脂肪に取り込ませる働きがあります。このインスリンが血液の中で適切に働くことで、血糖値が安定するのです。
インスリンが十分に作用されない原因は2つあります。
①必要な量が出ていない状態 =「1型糖尿病」
膵臓のインスリンを造る細胞が壊されている状態です。若年から発症する方が多く、自己免疫(体に入ってきたウイルスなどから体を守る働き)が異常をきたすため、発症すると考えられています。症状が急激に現れてくることも特徴の一つで、インスリンを注射などで補給しないと命に関わるような病態です。
②必要な量は出ているが十分な効果を発揮していない状態 =「2型糖尿病」
遺伝や生活習慣の乱れが関与していると考えられています。いわゆる「生活習慣病」の一種です。中高年に多く、症状がない方も多くいます。治療の基本は食事と運動習慣の改善で、それでもうまくコントロールできていない場合、薬を使用します。
今回は生活習慣病の一種である、「2型糖尿病」についてまとめています。
糖尿病の診断基準と症状
糖尿病は健康診断などで採血を行った際に、初めて指摘されることが多いと言われています。採血の項目の中で、糖尿病の診断に関わるのは、以下の2つになります。
★血糖値
検査した時の血糖の濃度。空腹時で126mg/dLを超えると糖尿病の疑いがあります。
★HbA1c (ヘモグロビン・エーワンシー)
過去1〜2ヶ月分の血糖値を反映します。6.5%を超えると糖尿病の疑いがあります。
この2つの項目を総合的に判断され、糖尿病と診断されます。
他にも、献血に行くと計測してもらえるグリコアルブミン(基準値:11〜16%)も、糖尿病の診断のきっかけになることがあります。
糖尿病の症状と合併症
血糖値が高くなると、以下のような症状が出ると言われています。
- 喉が乾く、水をよく飲む
- 尿の回数が増える
- 体重が減る
- 疲れやすくなる
血糖が非常に高くなると、意識障害を起こす可能性もある怖い病気です。
さらに怖いのは合併症です。
血糖が高い状態が何年も続くと、血管が傷ついたり、詰まったりしてしまい、様々な合併症を引き起こします。
細い血管に傷がつくと起こる合併症は、以下の3つになります。神経、目、腎臓のかしらもじをとって「しめじ」という覚え方もあります。
糖尿病性神経障害
神経には‘感覚神経’と‘運動神経’の2つがありますが、これらのいずれも障害される可能性があります。糖尿病が進行して起こる神経障害の最も特徴的なものは、手袋靴下型と呼ばれています。左右対称で、手袋をつけ、靴下を履いたような異常感覚を指します。
ほかにも、心臓の神経に障害があると、心筋梗塞を発症しても胸の痛みが起きないこともあります。
糖尿病性網膜症
目の中にある網膜(光の情報を脳に送る役割を担っています)にある血管が障害され、起こる症状です。重症化すると網膜出血などを起こし失明する可能性があります。日本における失明の3番目に多い原因と言われています(1番は緑内障)。
糖尿病性腎症
糖尿病が長期間にわたると腎臓の機能が徐々に低下していきます。現在、日本の血液透析に至る原因で1番多い病気は糖尿病性腎症と言われています(日本透析医学会 わが国の慢性透析療法の現況)。
また、尿の中に糖分(アルブミン)が漏れ出ている状態だと、心臓病になる可能性が高くなることもわかっています。
腎臓の基本的な機能や検査、心臓病との関わりについてはこちらも参考にしてください。
また、糖尿病は足・脳・心臓などの比較的大きな血管の「動脈硬化」を引き起こします。足の細い血管が詰まって壊死してしまったり、脳梗塞や心筋梗塞などにもなる可能性があります。
糖尿病治療のキホン
糖尿病の治療の目的は、血糖値を適切な値にコントロールし、合併症を起こさないことです。もし、合併症がすでにある方は、それ以上悪くしないことが重要です。
そして治療の基本は「食事」と「運動」です。これは、どちらかだけを気をつけていればいい、というものではありません。2つセットで改善する必要があります。
食事
食事の改善、といっても難しいことは特にありません。
適正なエネルギー量で、バランスのいい、規則正しい食事をとることが重要です。
適切なエネルギー量は、以下の式が用いられます。
1日の適切なエネルギー量(kcal)=目標体重(kg)×エネルギー係数
- ※目標体重=身長(m)×身長(m)×22〜25
- ※エネルギー係数
- 座っている時間が多い人=25〜30
- 家事や軽い運動を行っている人=30〜35
- 力仕事や活発な運動習慣のある人=35〜
実際にどれくらいのエネルギー量が必要か、今の自分の食生活に問題がないかどうかは、専門家である管理栄養士に相談することをお勧めします。
運動
運動を行い筋肉への血流が増えると、ブドウ糖は細胞の中に取り込まれ、インスリンの効果が高まります。また筋肉の量が増えることも、インスリンの作用を高めることにつながります。
運動の基本は、「有酸素運動」と「筋力トレーニング」です。
「ややきつい」と感じる強度で、可能であれば毎日、1回あたり20〜60分行うことが進められています。心臓病の方に勧められている運動と同じです。
運動は継続が一番重要です。まずは座りっぱなしの時間を減らすことから徐々に始めることも有効です。
食事や運動を改善しても血糖値がうまくコントロールできていない場合、糖尿病の薬が使用されます。最近では、糖尿病の治療薬であるSGLT2阻害薬が、心臓病の治療薬としても用いられています。
気をつけること
糖尿病の治療薬を内服している場合、かえって血糖値が下がり過ぎてしまう(=低血糖になる)可能性があります。人によって症状に差がありますが、低血糖になると、
- 冷や汗をかく
- 動悸がする
- 手足が震える
- 生あくびが出る
などの症状が出現することがあります。糖分を補充せず放っておくと命に関わることがある危険な状態であるため注意が必要です。
低血糖の対策としては、食事前や空腹時の運動を避けたり、飴玉やドラッグストアに売っているブドウ糖を携帯する、などが挙げられます。
高齢になると、低血糖時の症状を自覚しにくい場合もあります。「自分は一度も低血糖になったことがないから大丈夫」、と過信せずに、万が一に備えておくことも重要です。
まとめ
- 糖尿病は「インスリンの作用が十分でないためブドウ糖が有効に使われずに血糖値が普段より高くなっている状態」で血管を気づけて合併症を起こします。
- 心臓病の原因にもなります
- 治療の基本は「適切な食事」と「適切な運動」です
- 適切な血糖値を維持することで、合併症を予防する、もしくは悪化させないことが重要です