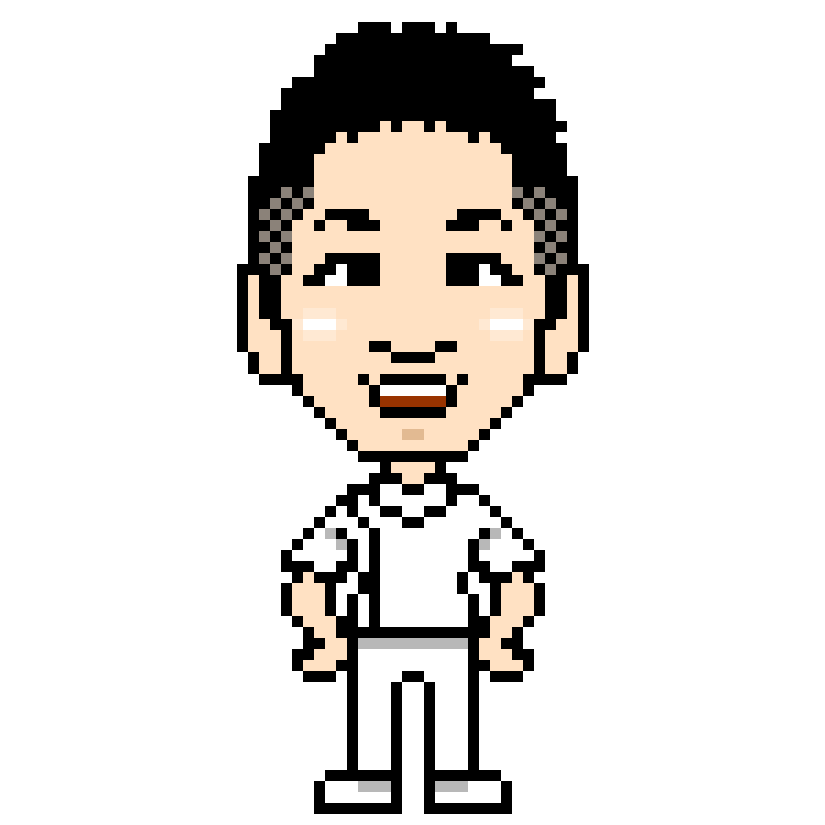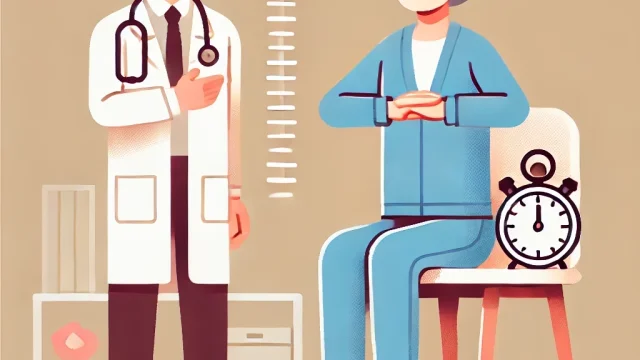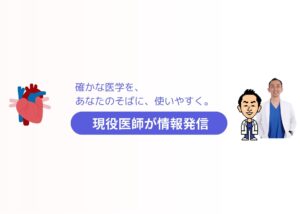筋力をつけることが重要なのはわかるのですが、なかなか時間が作れないんです。どれくらい筋トレをしたら効果が出てきますか?
アッキー
短時間の筋トレでも継続することで、しっかりと効果が得られる、という報告があります。ただし、いくつか注意点もあるんです。
毎日患者さんと関わっていると、「どれくらい運動をしたら、効果が出ますか」という質問をよくされます。心臓リハビリテーションのガイドラインで推奨されている「週3〜5日、1日40〜60分の運動」を実施することで効果が得られるのは間違いありません。
なかなか運動習慣が身につかない方に話を聞くと、「時間がない」「忙しい」といった理由が多いように感じます。
先日、‘’3秒筋トレ‘’といった記事を見つけました。これだけの時間で効果が得られるのであれば、普段の生活に運動を取り入れやすくなるな、と感じました。
今回は3秒筋トレの内容と、効果を上げるための頻度について、注意点を含めてまとめてみました。
3秒筋トレ 〜筋肉の動かし方を意識しましょう〜
Satoらの研究は、普段運動をしていない学生を対象に、肘を曲げる筋肉の筋力トレーニングを実施しています。筋力トレーニングは専用の機器(常に一定の速度で運動を行うことができる機械)を使用し、負荷はそれぞれの人が持っている最大の筋力を、1日1回、3秒間発揮する運動を、週5日、4週間継続しています。
ポイントは力の発揮の仕方(筋肉の動かし方)によって、結果が異なっている点です。
筋肉の動かし方にはの大きく3つの種類があります。
- 求心性収縮:筋肉が縮みながら力を発揮する運動
- 等尺性収縮:筋肉の長さは変わらず、力を発揮する運動
- 遠心性収縮:筋肉を伸ばしながら力を発揮する運動
この研究と同じ、肘を曲げる筋肉(主に、肘を曲げた時に力こぶができる筋肉)を例にすると、
- 求心性収縮は、肘を曲げて力こぶを作る動き
- 等尺性収縮は、肘を曲げて荷物を持っている時など、関節を同じ角度に保つ動き
- 遠心性収縮は、肘をゆっくりと伸ばす動き
となります。
この研究では、①〜③のそれぞれの運動を行った結果を比較しています。その結果、①・②では十分な効果は出ませんでしたが、③では筋力が改善した、と報告しています。
ちなみに、過去の筋トレの効果を比較した研究でも、③の遠心性収縮の方が、より効果が高かった、という報告が多くあります。
つまり、筋トレをより効率よく行うには、筋肉をゆっくりと伸ばす方向に動かすことが効果的、ということになります。
普段の筋トレでは専用の機器がないため、この研究と同じトレーニングを実施することは難しいです。ただし、おもりや自分の体重を使って、動かし方を意識することで同じ筋肉の使い方はできます。
いくつか例を挙げると、
- 肘を曲げる筋肉(主に上腕二頭筋):おもりを持ってゆっくりと肘を伸ばす動きを意識する
- 太ももの前の筋肉(大腿四頭筋):座って膝を伸ばす運動の場合、膝を曲げるときにゆっくりと戻すように意識する
- ふくらはぎ(腓腹筋、ヒラメ筋など):踵上げの運動の場合、踵をおろすときにゆっくりと下ろすように意識する
のようになります。
最大筋力を発揮することも難しいので、その分回数を多くこなす必要があります。
「ややきつい」と感じるくらいの回数を実施することをオススメします。
3秒筋トレ 〜効果的な頻度〜
Yoshidaらは、先ほどの研究結果を踏まえて、1週間あたりの実施頻度を変えて効果が得られるかを検討しています。運動方法は、先ほどの3秒筋トレと同じで、参加者それぞれの最大の筋力を発揮する遠心性収縮のトレーニングを1日1回実施しています。
この研究では、3秒筋トレの実施頻度を、週2回、週3回、週5回の3つのグループに分け、それぞれの筋力増強効果を比較しています。
その結果、週3回以上行うと筋力が増強し、週3回よりも週5回実施する方が、筋力はより大きく増強する結果となりました。
また、Yoshidaらは、同様のトレーニングを
- 1日6回、週1回だけ行うグループ
- 1日6回、週5日間行うグループ
- 1日6回×5セット、週1日だけ行うグループ
の3つグループで比較しました(1週間あたりの実施回数は②と③は同じ30回となっています)。トレーニング期間は4週間です。
その結果、③の週1日だけ30回実施するグループは筋力が改善しなかったのに対し、②1日6回、週5日間実施したグループは筋力が改善していました。
以上の2つの結果から、1日だけ頑張って数多くトレーニングをするよりも、1週間あたりの実施頻度を多くする、最低でも週3日以上行う方が、より筋力の改善効果を得られる、ということになります。
注意点
これらの報告について、いくつか注意してほしいことがあります。
まず、対象者が健康な若い人である点です。高齢者は心臓病だけでなく、関節痛などを合併している可能性があります。この研究では、このような合併症がある方へトレーニングを行う際の安全性について検討はされていない点です。
また、最大の筋力を3秒間発揮し続ける際、ついつい息をこらえてしまう可能性があります。息をこらえながら力を発揮すると、胸の中の圧力が上昇し、運動開始直後に血圧も上昇します(運動中、血圧が過剰に下がる瞬間もあります)。これを‘’バルサルバ効果‘’と言います。血圧が上昇すると、心臓に負担がかかりすぎてしまい、心臓病が悪化する可能性があります。心臓リハビリテーションのガイドラインでも、筋トレを行う際の注意点として記載してあります。対策として、数を数えながら行うと、息こらえを予防することができます。
普段運動習慣がない方や、筋力が低下している方に、強い強度のトレーニングを行うと、後から遅れて筋肉痛が生じる可能性があります(これを、遅発性筋痛といいます)。遅発性筋痛は、今回のトレーニングのような、筋肉を伸ばしながら行うトレーニングの際に出現しやすいとされています。また、この痛みが出てきた際、筋力も同時に低下することがわかっています。対策としては、①運動前後にしっかりとストレッチを行うことと、②軽い運動から徐々に体を慣らしていくこと、が重要です。
インターネットや本、テレビなどで様々なトレーニング方法が紹介されていますが、基本は安全第一。心臓病の方には安全な運動を軽い負荷から導入することが重要です。運動強度は慣れてきてから徐々に上げるようにしましょう。運動の基本や、筋トレの効果を高める食事についてはこちらも参考にしてください。
運動中の心拍数や血圧の変化、不整脈が出ないかなどを確認するために、まずは医療機関で行われている心臓リハビリテーションに参加することが望ましいです。
また、アップルウォッチでは心拍数が計測できたり、不整脈を完治する機能もあります。あまり心拍数が上がりすぎてしまうと、かえって心臓に負担がかかりすぎてしまうため、適切なタイミングで休憩を取ることも重要です。
現在、循環器専門医がApple watch専用の運動支援アプリを開発中です。
循環器専門医の脈拍に基づいた運動強度の設定のノウハウと、Apple watchの精度の高い脈拍計測を掛け合わせた世界で初めてのアプリです。
脈拍が高くなりすぎて心臓に負担がかかりすぎている時に通知して教えてくれる機能があります。
ご興味がある方は、以下のLINEにお友達登録をお願いいたします。開発状況など最新情報を共有いたします。

まとめ
- 負荷が高い方が筋トレの効果は得られやすいですが、まずは安全な強度から開始しましょう。
- 筋トレは少なくとも週3日以上行うことが重要です。
- 安全な運動を行うために、まずは医師や理学療法士に相談の上でメニューを調整することが望ましいです。