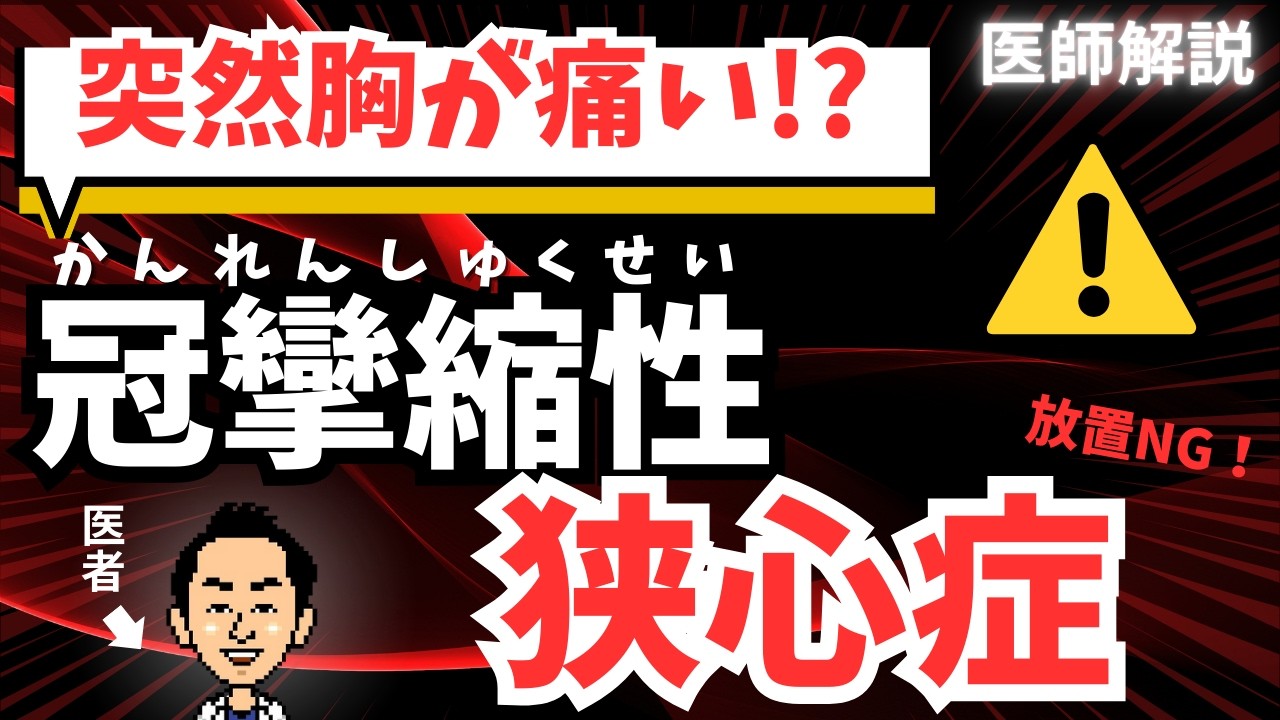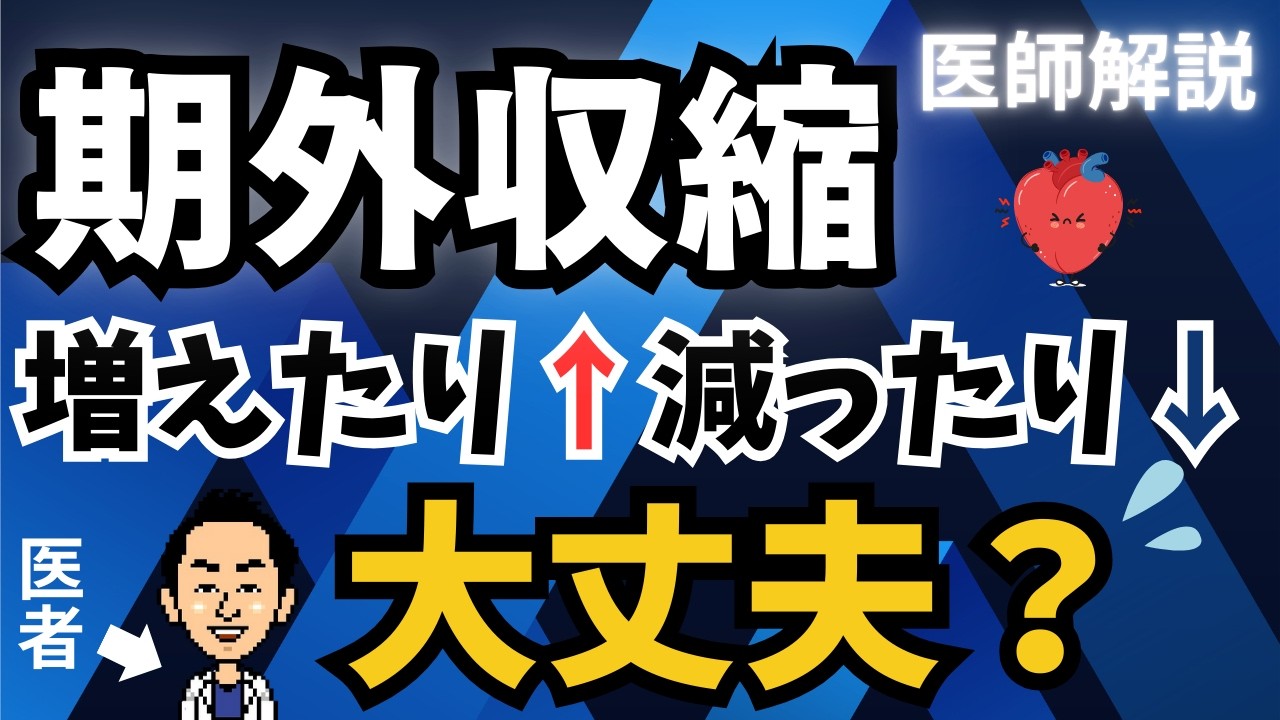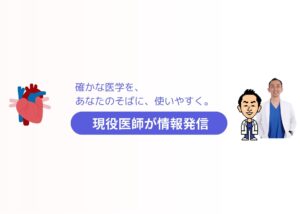🎥 YouTubeでも動画で解説しています。視覚的に理解したい方はこちらをご覧ください:
【専門医解説】冠攣縮性狭心症とは?
はじめに:冠攣縮性狭心症とはどんな病気?
こんにちは、循環器専門医のまるです。
今回は「冠攣縮性(かんれんしゅくせい)狭心症」について、できるだけ分かりやすく解説していきます。
おそらくこのページを見ているあなたは、ご自身やご家族がこの病気と診断されたのではないでしょうか?
名前だけでも難しそうな病気ですが、実際の仕組みを理解することで、日々の対策や治療に前向きに取り組むことができます。
私の母もこの病気と診断されました。だからこそ、皆さんの生活に役立つよう丁寧にお話ししていきます。
冠攣縮性狭心症の仕組みをわかりやすく解説
難しい漢字をひもとくと…
- **「冠」**は冠動脈(心臓の筋肉に栄養を届ける血管)
- **「攣縮」**はギュッと縮むこと
- **「狭心症」**は心臓が血液不足になる状態のこと
つまり、冠攣縮性狭心症とは「心臓の血管が急に縮んでしまい、その結果、心臓に必要な血液が届かなくなり、胸の痛みなどが起こる病気」です。
血管はホースじゃない!?動く「筋肉の管」
血管の壁には「平滑筋(へいかつきん)」という筋肉があって、これが収縮と弛緩を繰り返しながら血管の太さを調節しています。
この筋肉が突然収縮して血管が狭くなると、血流が減って心臓に十分な酸素が届かなくなり、胸の痛みが出るのです。
足がつるのと似ている現象
実は、この仕組みは「足がつる」のとよく似ています。
自分の意思とは関係なく、筋肉が勝手に収縮してしまうんですね。冠動脈でも同じようなことが起きるのです。
命に関わる病気なの?
残念ながらはい、命に関わる可能性のある病気です。
心臓に必要な血液が届かない「虚血(きょけつ)」状態になると、不整脈が出やすくなり、心臓の働きが不安定になります。
これが進むと、突然死につながることもあるため、放っておくことは絶対にできません。
治療法について
血管を拡げる薬で対応
- 発作時:ニトログリセリン(ニトロ)を使って血管を拡げる
- 発作が頻繁な場合:カルシウム拮抗薬などの内服薬を毎日服用
発作の頻度が少なければ、発作時のみニトロを使用することもありますが、「発作自体を起こさない」ことが本質的な目標です。
発作を防ぐ生活習慣とは?
発作を引き起こす「誘因」を避けることが重要です。中でも特に注意すべき3つがこちら:
1. 禁煙
タバコに含まれる成分は冠動脈の収縮を引き起こす原因になります。禁煙は最優先事項です。
2. アルコール制限
アルコールも発作の引き金になります。
特にお酒を飲むと顔が赤くなるタイプの方は、リスクが高いことがわかっています。
3. ストレス対策
精神的なストレスも発作を引き起こす大きな要因です。
「職場を変える」など現実的に難しいこともあるかと思いますが、対処法はあります。
日常に取り入れたい「運動習慣」
ストレスの軽減や血管の健康を保つために、適度な運動が推奨されています。
運動ガイドラインの目安(日本循環器学会より)
- 中強度~高強度の有酸素運動を30分以上、週3回以上
- 早歩きなどの全身運動を週140〜180分程度
無理なく続けることが大切です。
ただし、運動のしすぎも要注意。高すぎる負荷は逆に発作を誘発することもあるため、「中強度」を意識して安全に行いましょう。
無料テキストでさらに理解を深めましょう
冠攣縮性狭心症を含む心臓病について、専門医が100ページ以上にわたって執筆した無料のテキストをご用意しています。
生活に役立つ運動の解説や、病気のイメージを掴みやすくなる内容が満載です。
LINEに登録するだけで簡単にダウンロード可能!
👉 無料テキストはこちらから:
https://lin.ee/GtAuySW
まとめ
- 冠攣縮性狭心症は、冠動脈が突然収縮して心臓の血流が不足する病気
- 放置すると命に関わる不整脈や突然死の原因になることも
- 治療は主に血管を拡げる薬、そして誘因の排除が重要
- 禁煙・節酒・ストレス対策がカギ
- さらに、適度な有酸素運動も生活に取り入れましょう
これらを実践しながら、安心して毎日を過ごしていただければと思います。
今日も、健康であなたらしい一日を!